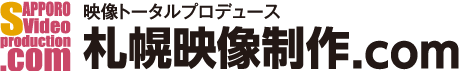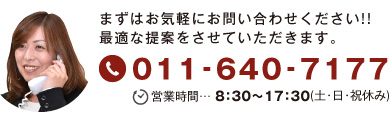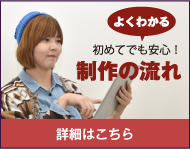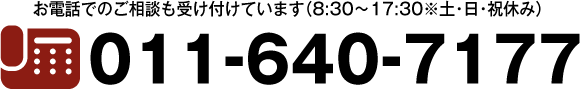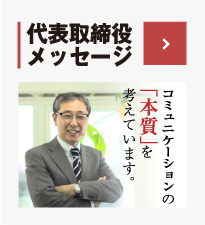社長メッセージ

弊社は創業から60年強、「つながる~つたわる」をコンセプトに、企業が消費者・クライアントとつながるためのコミュニケーション活動のサポートを行ってきました。
改めて、『コミュニケーション』とは、一体何でしょうか?
ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典によると、
『言語,身ぶり,画像などの物質的記号を媒介手段とした精神的交流のこと。語源はラテン語で「分かち合う」を意味する communicare。歴史的には物質的記号は初期の身ぶり,叫びなどの直接的で無反省な状態から,明確な言語などの普遍的かつ間接的な状態へと発達した。(中略)生物学用語としては,動物の同種個体間にみられる種々の信号のやりとりをさす。動作や色彩や光などの視覚的,鳴き声などの聴覚的,匂いなどの嗅覚的信号が用いられる。同種個体は一般にその信号に対して本能的に反応することが多い。』
また、デジタル大辞泉によると、『1 社会生活を営む人間が互いに意思や感情、思考を伝達し合うこと。言語・文字・身振りなどを媒介として行われる。
2 動物どうしの間で行われる、身振りや音声などによる情報伝達。
[補説]「コミュニケーション」は、情報の伝達、連絡、通信の意だけではなく、意思の疎通、心の通い合いという意でも使われる。「親子の―を取る」は親が子に一方的に話すのではなく、親子が互いに理解し合うことであろうし、「夫婦の―がない」という場合は、会話が成り立たない、気持ちが通わない関係をいうのであろう。』
とあります。
コミュニケーション活動のサポートを生業としている弊社は、一般消費者と企業の『分かち合い』=『心の通い合い』のお手伝いをしてきたことになります。

我が国の広告の歴史をたどってみると、江戸時代では各商人が店の軒先に「看板」を競って掲げ、チラシの代わりとなる「引札」を広く配布し、顧客獲得にまい進してきました。
明治時代に入ると、新しい媒体として「新聞・雑誌」が登場し、マスメディアを用いた近代的な広告活動がスタートしました。この時代に、西洋から導入された活版印刷によって安価で大量に印刷される新聞は、多彩な情報を広く・効率よく伝達できる広告メディアとして中心的な地位を獲得し、新聞広告を取り次ぐ広告代理業の発達を促しました。またこの時期には、新しい石版印刷技術が普及し、彩り豊かな絵、「びら」や「ポスター」なども登場しました。
大正時代に入ると、日本経済の発展を背景に都市化が進み、華やかな大正モダニズムが開花しました。国民の生活スタイルがどんどん華やかになったのもこの時代です。
昭和に入ると、消費の高度化・大衆娯楽の成立などを背景に、商業美術も発展を遂げました。しかし、次第に戦時色の強まる中で消費経済が圧縮され、戦意高揚を目的とした国家による宣伝活動が活発化し、広告は冬の時代へと入っていきました。
敗戦により焦土と化したわが国は、国民の旺盛な意欲に支えられ、急速に復興・経済成長へと走り出しました。その一翼を担う広告は、まず新聞・雑誌広告が復活しました。昭和26(1951)年には新しいマスメディアとして商業放送である「民間ラジオ局」が開局し、2年後には初の「民間テレビ局」が開局しました。やがて、電波メディアは主力広告メディアとしての地位を確立していくことになります。ちょうどこのころ、1953年(昭和28年)に創業した弊社は、「紙」を始めとした二次元媒体を通じて、一般消費者と企業のコミュニケーション活動のサポートを北海道室蘭の地でスタートいたしました。
昭和39(1964)年のオリンピック東京大会を契機に、テレビ受像機の普及率は90%を超え、ラジオ、新聞、雑誌とともに4大マスメディアの時代が到来しました。

おりから、高度経済成長に伴う消費の爆発的拡大を背景に、大量生産、大量販売、大量消費を実現するマーケティング活動が本格化し、広告は躍進期を迎えます。
日本経済が安定成長へと移行する中で消費に対する欲求の高度化や多様化が進行し、広告は「マスメディアを駆使した広告活動」と「多彩なプロモーション活動」を一体化した、より戦略的で多様な活動へと発展していきました。1990年代に入るとバブル経済が崩壊、経済不況が深刻化する一方で「資源・環境」に対する関心が高まり、新しい時代を模索する動きが本格化しました。
1995年には「Windows95」が日本において発売され、「インターネット」が普及します。パソコンが一人一台当たり前のように持つ時代になりました。
そして、2000年代に入ると、携帯電話が一人一台当たり前に持つ時代になり、2000年代後半には、i-phoneを始めとした「スマートフォン」が普及し、インターネットという媒体が「人」と「場所」を選ばずに利用できるようになりました。
同時に、通信環境が発達し、文字データだけでなく、画像は当然のこと、映像・動画がより身近になり、企業が消費者へ伝達する手段が多種多様に広がりました。
このように、媒体の歴史と、コミュニケーション、つまり「心の通い合い」の歴史は密接にリンクしております。
媒体・コミュニケーション手法の進化とともに、我々もコミュニケーション手法の進化を止めるつもりはありません。
紙を否定するわけではなく、より現代に適した「心の通い合い」の方法として、映像・動画制作を展開することとなりました。
今後は、この『札幌映像制作.com』を通して、北海道という地において、最新の「心の通い合い手法」を紹介するとともに、未来の「心の通い合い手法」を提案してまいります。
是非ご期待いただくとともに、温かい目と声で本サイトを育てていただけますと幸いです。
代表取締役